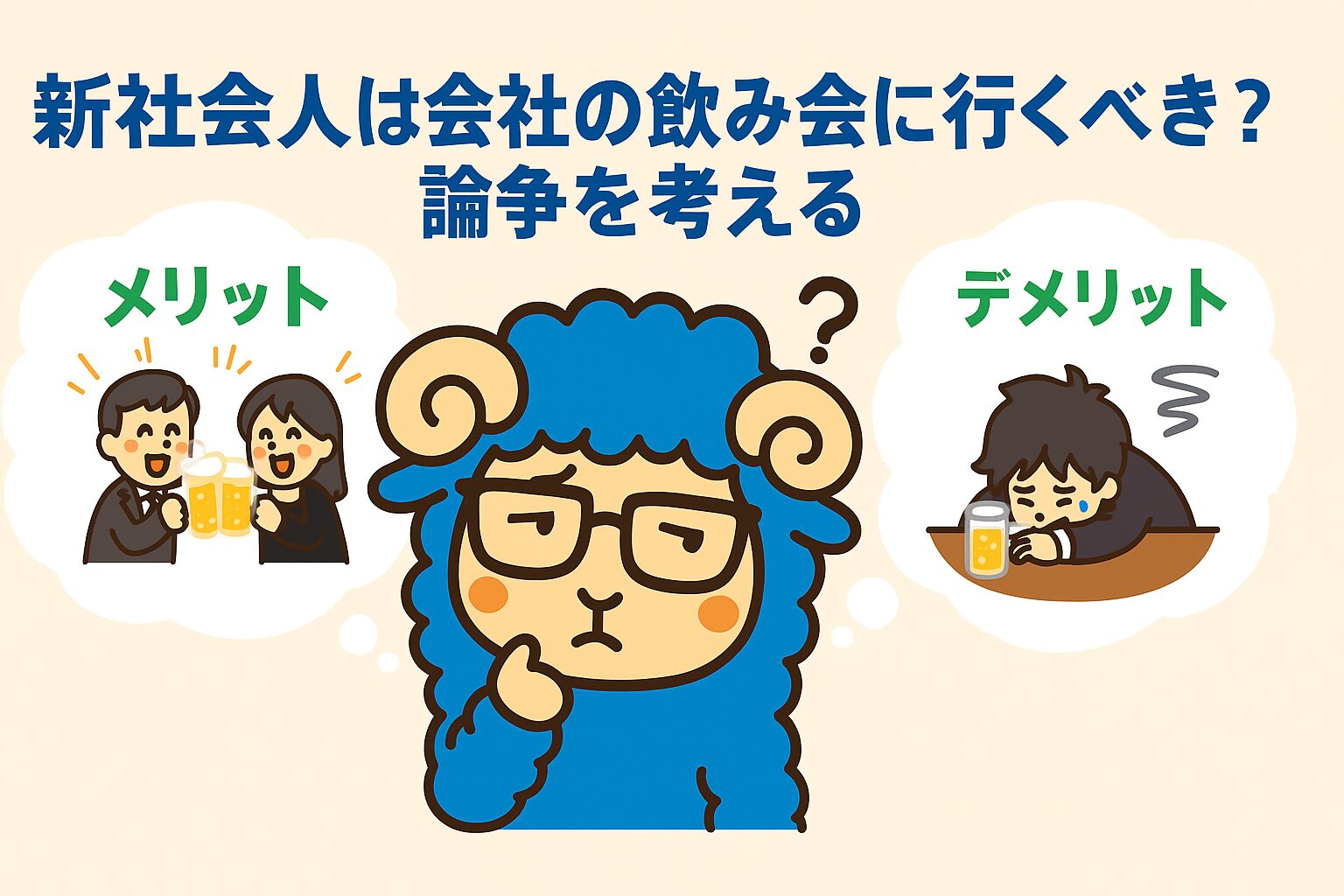皆さんこんにちは!みとんです。
新社会人の皆さんは会社の飲み会についてどう思っていますか?
- 「飲み会に行かないと出世できない」
- 「飲み会なんて時間とお金の無駄」
このテーマは、毎年のように議論になる定番ネタ。春になるとSNSでも必ず話題になります。
結論から言うと、どちらも“半分正しい”のです。
今回は、僕が社会人1年目を経験して感じたことを交えながら、「飲み会にどう向き合えばいいか」について考えていきたいと思います。
飲み会は何のためにあるのか?

まず大前提として、会社の飲み会は何のために存在しているのでしょうか。
結論から言うと、コミュニケーションを深めるためです。
- 日常業務で関わりの少ない人と話せる
- 上司や先輩の人となりを知れる
- プライベートの一面を見せ合える
- 普段しにくい相談や本音トークができる
僕自身も、普段オフィスではほとんど話さない先輩と飲み会で意外な趣味が共通していたことをきっかけに仲良くなり、その後は仕事でも頼りやすくなった経験があります。
つまり飲み会の本質は「お酒を飲むこと」ではなく、「人間関係をつくる場」なんです。
Z世代が飲み会を敬遠する理由

最近「Z世代は飲み会に行かない」というニュースや記事をよく目にします。
なぜでしょうか?
理由はシンプルで、その飲み会に価値を感じられないからです。
飲み会に行くにはお金と時間を使う必要があります。社会人にとって時間もお金も有限。だからこそ「払う価値があるか」をシビアに判断しているのです。
Z世代が抱く飲み会のイメージはこんな感じではないでしょうか。
- 上司に常に気を使わないといけない
- 説教タイムになる
- 「これだから最近の若い子は」と年齢差別的な発言をされる
- 延々と続く上司の武勇伝・昔話
これでは「お金を払って参加する価値がある」とは思えませんよね。
むしろ「仕事の延長戦」と感じてしまい、断りたくなるのも自然なことです。
飲み会に参加するメリット

それでも、飲み会に参加するからこそ得られるものも確実にあります。
1. 上司や先輩との距離が縮まる
飲み会では仕事以外の話が増え、プライベートの人間関係が築けます。
僕も「これまで話しかけづらかった先輩」が、飲み会をきっかけに気軽に話せる存在に変わりました。翌日から仕事がスムーズになったのを実感しました。
2. 普段聞けない業界知識やキャリアの話が聞ける
「どうしてこの部署に異動したのか」「若いころはどう働いていたのか」など、職場ではなかなか聞けないことを聞けるのは貴重です。
意外とキャリア形成のヒントになる話も多いです。
3. 共通体験が信頼を生む
一緒にお酒を飲み、同じ時間を過ごすことは「共通体験」として記憶に残ります。
人は共通体験を重ねることで距離が縮まる生き物です。
そこから信頼が生まれ、仕事の相談や協力につながることもあります。
飲み会のデメリット

もちろん、良いことばかりではありません。
- 金銭的負担
新人にとっては4,000円が大きな出費。
上司世代と同じ金額でも負担感がまったく違います。 - 時間的拘束
2時間以上は当たり前。
二次会があればさらに長く、翌日の仕事に影響する可能性も。 - ハラスメントのリスク
少なくなったとはいえ「飲め飲め!」という空気や、不適切な発言がゼロとは言えません。
これらのリスクがある以上、「無理に参加しろ」というのはもう時代に合わない考え方です。
最近の変化

ここ数年で飲み会に対する風潮も大きく変わってきました。
- 強制参加はNG:多くの企業で「飲み会は自由参加」と明文化
- 多様なスタイル:ランチ会、オンライン飲み会、カフェで雑談など
- Z世代の声:「飲み会が嫌いなのではなく、意味のない飲み会に行きたくない」
つまり、Z世代も交流を求めていないわけではなく、「価値を感じられる場」であれば積極的に参加するのです。
新社会人への提案

僕の経験を踏まえて、新社会人に向けたアドバイスは次のとおりです。
- 最初の1回は出てみる
雰囲気を知る意味で一度は経験してみるのがおすすめ。
0回と1回では周囲の印象が大きく違います。 - 断り方もスキルのひとつ
「予定があって難しいですが、誘ってくださってありがとうございます」と感謝を添える。
これだけで印象はまったく違います。 - 代替案を示す
「お酒は苦手ですが、今度ランチでぜひお話したいです!」と伝えれば、交流の意思を見せられます。
上司・先輩への提案

若手が「行きたい」と思える飲み会をつくるのも先輩の役割です。
- ランチから始める:いきなり2時間の飲み会はハードルが高い
- 最初の1回はごちそうする:金銭的負担を減らしてあげると参加しやすい
- 仕事の話は控える:重い雰囲気を避け、フラットに交流する
- 若手に話を振る:置き去りにせず参加感を持たせる
こうした工夫ひとつで、飲み会は「義務」から「楽しみ」に変わります。
まとめ

飲み会に行くかどうかは、最終的には個人の自由です。
Z世代が断る理由にも十分な背景があります。
重要なのは、
- 上の世代が「どうすれば若手が参加したくなるか」を考えること
- 若手も「ただ断る」のではなく誠意を持って対応すること
世代間の価値観の違いはなくせません。
しかし、お互いを尊重し理解しようとすることで、心地よい関係性と働きやすい環境は作れるはずです。