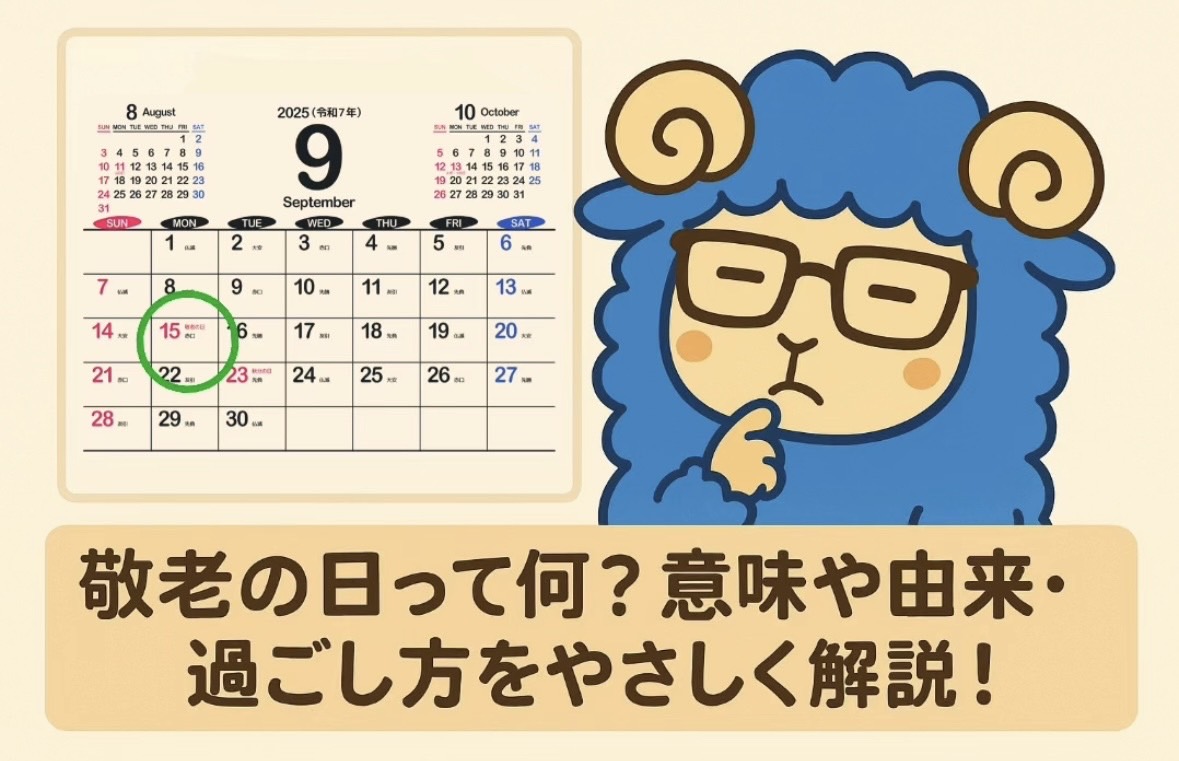皆さんこんにちは!みとんです。
9月になると、カレンダーに赤い日が並んでいるのを見て「おっ、今月は連休があるぞ!」とちょっと嬉しくなりますよね。
特に9月の第3月曜日は、学校や会社が休みになる人も多いので、3連休になることもしばしば。
でもふと考えてみると、
「この休みって何の祝日だっけ?」
「たしか…敬老の日?」
と思うことはありませんか?
名前は知っているけれど、具体的にどんな意味を持つ日なのか、どうして祝日になったのかまではよく知らない人も多いと思います。
今回は、そんな敬老の日の由来や意味、今の過ごし方までをじっくり紹介していきます。
敬老の日とは?

まずは基本から。
敬老の日は、国民の祝日として「多年にわたり社会につくしてきた老人を敬愛し、長寿を祝う日」と定められています。
つまり、長い人生を生き抜いてきたお年寄りを敬い、その知恵や経験に感謝し、元気で長生きしていることをお祝いする日というわけです。
日本は古くから「年長者を大切にする文化」がありますが、その精神を現代に受け継いだ祝日だとも言えます。
敬老の日の始まり
実はこの祝日、最初から国が決めたものではありませんでした。
始まりは1947年、兵庫県多可郡野間谷村(現在の多可町八千代区)です。
当時の村長・門脇政夫さんが「老人を大切にし、その知恵を借りて村づくりを進めよう」と提案し、9月15日を「としよりの日」と定めてお祝いをしたのが最初でした。
その取り組みは「いい考えだ」として兵庫県全体に広まり、さらに全国へ。
やがて1966年に国民の祝日「敬老の日」として制定されるに至りました。
つまり、小さな村の地域行事が、今や日本中で祝われる国民の祝日になったのです。
9月15日から第3月曜日へ
もともと敬老の日は「毎年9月15日」でした。
しかし2003年、祝日を月曜日に移して連休を増やす「ハッピーマンデー制度」が導入され、現在の「9月の第3月曜日」に変更。
この移動によって、3連休が生まれる年もあり、「シルバーウィーク」と呼ばれることもあります。
ただし「9月15日が敬老の日だった」という記憶を持つ世代の人も多く、今でもその日に合わせて行事を行う地域もあります。
敬老の日の過ごし方
現在の敬老の日は、家族で過ごす温かい行事の日として定着しています。
- 孫からおじいちゃん・おばあちゃんへ手紙やプレゼントを贈る
- 家族そろって食事をする
- 自治体が長寿を祝って記念品を贈る
- 学校や地域で「お年寄りに感謝を伝える行事」が行われる
こうした習慣を通して、世代を超えたつながりを感じられる日にもなっています。
海外にも似た祝日はあるの?
「お年寄りを敬う」という文化は、日本だけのものではありません。
世界にも高齢者を大切にする記念日があります。
- アメリカ
9月の第1日曜に「Grandparents Day(祖父母の日)」があります。1978年に制定され、孫から祖父母に感謝を伝える日とされています。 - 中国
旧暦9月9日は「重陽の節句」。昔から長寿を願う日で、高齢者を敬う意味も込められています。 - 韓国
5月8日は「父母の日(オボイナル)」で、両親を敬い感謝を伝える日。日本の母の日・父の日が合体したような行事ですが、高齢の両親を中心に祝う点で敬老の日と近い雰囲気があります。 - 国連
1990年に「国際高齢者デー(International Day of Older Persons)」が制定され、毎年10月1日に世界的に高齢者を尊重する日とされています。
こうして比べてみると、高齢者を敬い感謝する文化は世界共通の価値観だとわかります。
ただ、日本の敬老の日は「国民の祝日」として休日になっている点が特徴的です。
高齢化社会と敬老の日の意味
現代の日本は「世界一の長寿国」と言われ、2025年には65歳以上が人口の3割を超えると予測されています。
つまり「高齢者をどう支えていくか」が社会の大きなテーマになっているわけです。
そんな時代だからこそ、敬老の日には二つの意味があると考えられます。
- 感謝を伝える日
今まで社会を築き、次の世代に多くを残してくれたことへの「ありがとう」を伝える。 - 世代をつなぐ日
お年寄りの知恵や経験を学び、子や孫がそれを受け継いでいくきっかけにする。
単に「長生きおめでとう」というお祝いだけでなく、世代のつながりを再確認し、未来を考える日としての意義も広がっているのです。
まとめ
「ラッキー!休みだ!」から始まる敬老の日。
でもその背景には、地域の小さな取り組みが全国に広がった歴史や、日本人が昔から大切にしてきた「年長者を敬う心」があります。
ちょっとした由来を知るだけでも、この日の過ごし方が少し変わるかもしれません。
普段なかなか言葉にできない感謝の気持ちを、家族やお世話になった人に伝えるきっかけにしてみるのも素敵ですね。